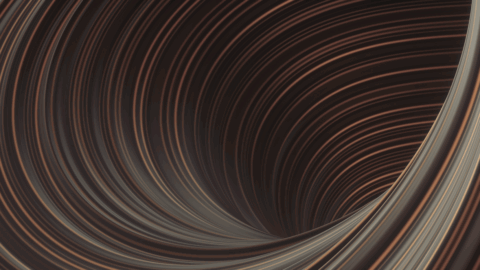人手不足社会を乗り越え、「地域の足」を守る
2025年4月中旬の昼下がり、JR 常陸多賀駅を出発したバスは、BRT(バス高速輸送システム) 専用道区間「ひたちBRT」に入ると自動運転に移行した。運転手がハンドルから手を離した状態でも、ハンドル、ブレーキ、アクセルが自動で制御され、なめらかに走行する。専用道はバス以外が侵入できない構造であるものの、ルート上には、14 か所のバス停、11か所の一般道との交差、15か所の歩行者が横断できる横断指導線があり、歩行者や自転車とのすれ違いなど、現実的な走行環境に対応しながら走っている。

BRT専用道内に存在する横断指導線(左)や一般道交差部(右)
「普通のバス」を自動運転化
みちのりグループの一員である茨城交通は、2025年2月、日本国内で初めて「レベル4」による中型バスの営業運行を遂に実現した。営業運行区間は6.1kmと、レベル4 では国内最長である。これは単なる技術実証を越えて、地域に根差した公共交通の持続可能なモデル構築に向けた大きな一歩である。
自動運転の実証実験は2018 年にスタートした。かつて日立電鉄線が走っていた線路跡に整備された「ひたちBRT」において、まずはシステムが人間の運転を支援する「レベル2(部分運転自動化)」から取り組みを開始。2022 年からは「レベル4(特定条件下での完全自動運転)」を見据えた実証に取り組み、段階的に技術を磨きあげてきた。
車両にはLiDAR(レーザーセンサー)、カメラ、GPS受信装置を搭載し、周囲の物体との距離・形・動きなどを瞬時に検知。例えば、歩行者が飛び出してきた場合には、減速や一時停止などの対応を自動的に行い、安全に配慮した運行を実現している。
茨城交通の自動運転化の取り組みの根底には、「普段のバスをそのまま自動運転化する」という発想がある。この発想は、先端技術でありながらも利用者にとっては違和感のない、社会実装を見据えたものであり、みちのりホールディングスの担当者は「非常に実効性の高い最先端の取り組みだと自負している」と語る。
課題に向き合い、先駆者として運行モデルを描く
とはいえ、本格的な社会実装に向けては自動運転ならではの特性に折り合いをつけていかなければならない。例えば2025年4月現在、自動運転区間の所要時間は約29分。人間が運転する場合の約20分と比べて時間がかかっているため、利便性の面での最適化が求められる。また、現行制度との兼ね合いで、乗車定員は28人に制限され、輸送効率の面でも課題がある。 さらには、日本各地で自動運転に向けた試みが個別に進んでいるために、車両もそれぞれで設計・装備されており、広域での社会実装に向けては標準化・量産化によるコストダウンが必要である。
自動運転の意義は運転そのものの代替だけに留まらない。今後は「省人化」、すなわち労働生産性を高めることが鍵となる。現在は、自動運転車両にも特定自動運行主任者(自動運転車両の動作状況を監視する役割で運転操作はしない)1名が乗車し、乗客対応や緊急時の避難誘導などの「車掌的な業務」も担っているが、将来的には、複数車両の遠隔監視・遠隔対応といった新たな運行モデルへの移行が求められる。
みちのりホールディングスは、こうした構造変革の先陣を切る存在として、自動運転の現場での知見を活かしながら、社会実装の壁を一つひとつ乗り越えていく。人手不足にあえぐ日本社会において、「地域の足」を守るという使命のもと、地方交通の未来を切り拓く挑戦は、これからも途切れることなく続いていく。